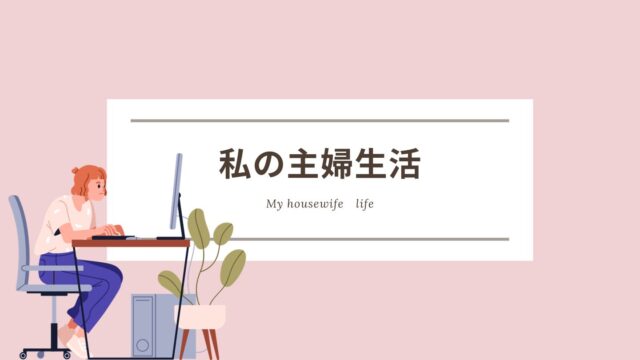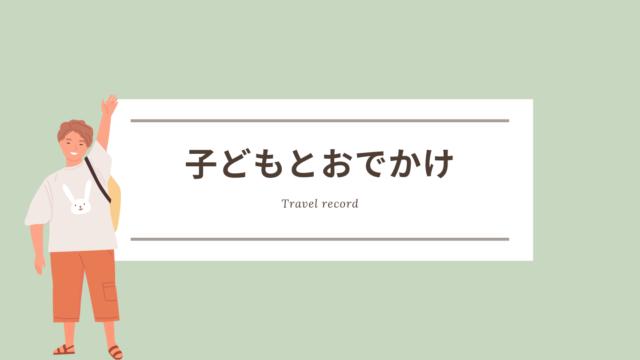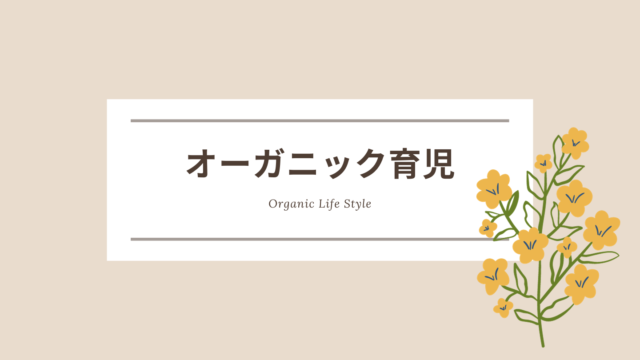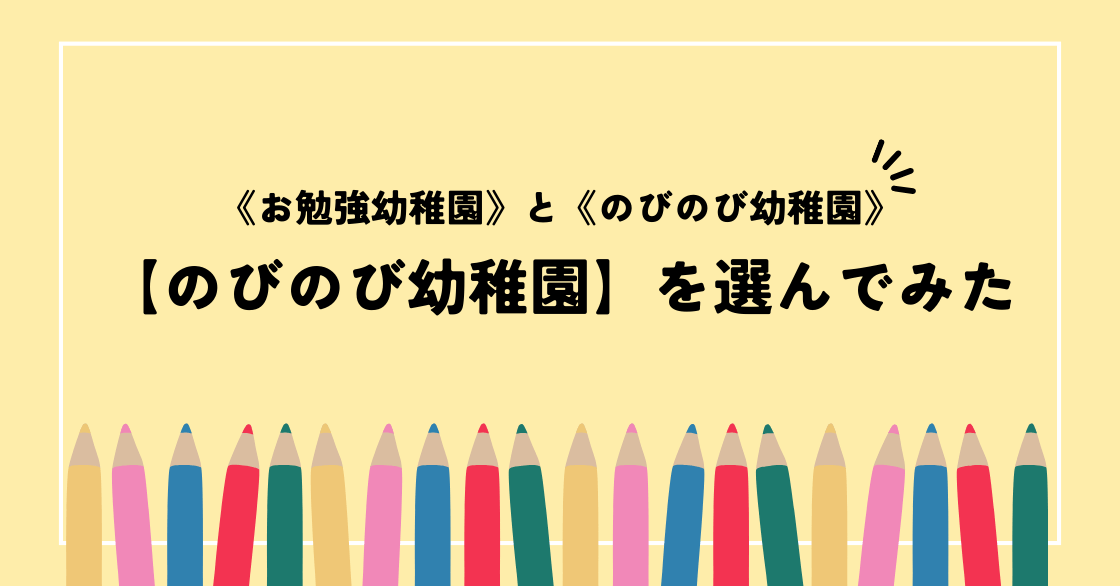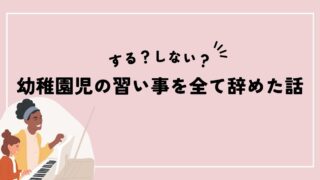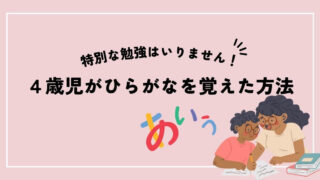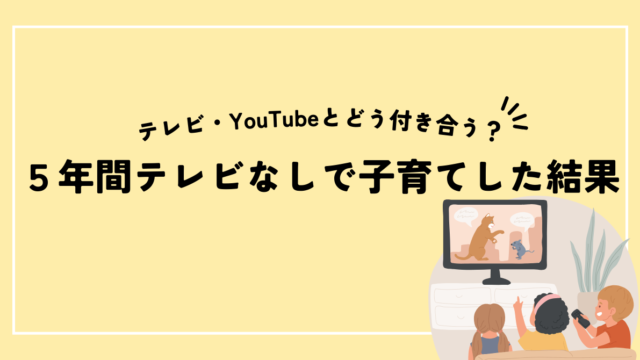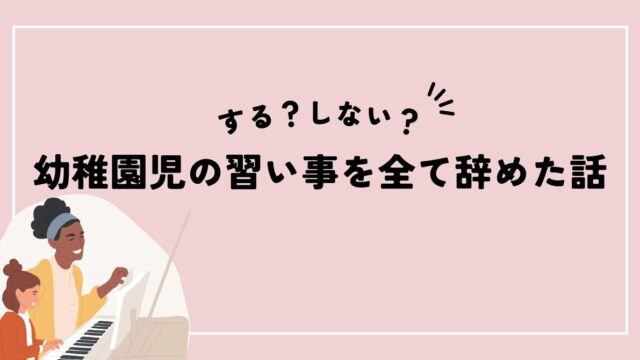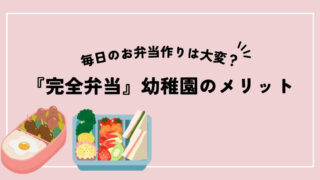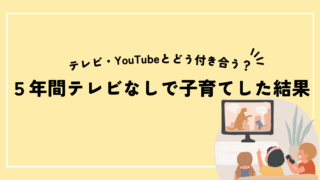こんにちはまいたけです。
一人っ子の長男をのびのび系幼稚園に通わせています!
《お勉強系幼稚園》と《のびのび系幼稚園》
みなさんはどちらがご自身のお子さんに合うと思いますか?
私は、息子の性格を踏まえてのびのび系の自由保育を重視した幼稚園を選びました。
この記事では、のびのび系幼稚園に通わせてみた私の感想を書きます。
《お勉強系幼稚園》と《のびのび系幼稚園》とは?
ネットで調べてみると、ざっくり違いはこんな感じ。
カリキュラムが整った幼稚園。
英語、リトミック、読み書き、体操など教育的な指導が充実した保育。
行事のクオリティも高い。
自由に遊ぶ時間が多い幼稚園。
特別な教育的指導は行わず、毎日好きな遊びを自由にのびのびと遊んで過ごしている。
行事のクオリティはそこまで高くない。
私の住む地域にはどちらの幼稚園もありました。
我が家が選んだのはのびのび系幼稚園。
一方、お隣に住む男の子はお勉強系幼稚園に通っていました。
なので話を聞いてみると、お勉強系幼稚園のカリキュラムには驚かされました。
《お勉強系幼稚園に通うお隣さんの話》
・全クラスに日本人の担任の先生と外国人の副担任の先生を配置。
・毎日英語の歌の練習
・お遊戯会は全生徒がそれぞれの楽器演奏
・体操や音楽の専門の先生が在籍していて日々指導
話を聞くと、子どもがもつ可能性を最大限引き伸ばそうとしてくれる様子が分かります。
特に共働きの家庭には人気なようで、『習い事を通わせなくても幼稚園の中で様々な経験をさせてもらえるカリキュラム』が評判のようでした。
活発なお隣のお子さんはお勉強系幼稚園がとても合ってるようでした!
私が《のびのび幼稚園》を選んだ2つの理由
①我が家の教育方針
我が家の教育方針のひとつは、
『幼児期には今しかできないことをする。』
子ども時代は本当にあっという間。
それなら、子ども時代にしかできない”遊び”をたくさんして欲しいというのが私の願いです。
読み書きやお勉強は、小学校に進学すればいずれできるようになります。
そのため、毎日の幼稚園での生活は『決められたカリキュラム』に縛られず、好きなことを自由にして欲しい思うのです。
子ども時代はとにかく自由に遊び尽くしてほしい!
②息子の性格
息子は言われたことをきちっとこなすのが好きな性格でした。
- 『着替えて』と言われればちゃんと着替える。
- 『ダメよ』と言われればすぐにやめる。
そんな姿を見たママ友たちからは、
『〇〇くんは子育ての成功例だね。』『〇〇くんって人生何周目なの?』
なんて言われることもありました。
しかし、私にとっては、そんな聞き分けの良い息子が、同時に心配でもありました。
もっと子どもらしくのびのびとしてほしい。
大人に抑圧されたり、よく見られようとする必要はない。
もっと自分勝手に生きてほしい。
そう思い、カリキュラムをこなすことが良いとされるのではなく、
自分の好きなことを自主的にすることが良しとされる幼稚園が良いと思いました。
《のびのび幼稚園》で良かったこと
①自分の思いを伝えられるようになった
幼稚園に入園したばかりの頃、息子は自分の思いを人に伝えるのが苦手な子どもでした。
お友達におもちゃを取られても、口をぎゅっと固くして、泣くのも我慢していたようです。
しかし、秋の保育参観では、自分の気持ちを表現する息子の様子を見ることができました。
その日の自由遊びの時間に、『先生、畑の金柑を食べに行きたい。』と先生に伝えて連れて行ってもらっていたのです。
周りに合わせることなく自分の思いを主張する姿に、とても成長を感じました。
自由遊びが中心の幼稚園では、『今日は何をして遊ぶのか』を自分で考えます。
『今日は〇〇をしたい!』と自分の気持ちのままに遊ぶことが許されているのです。
もし幼稚園の方針で、決められたカリキュラムを毎日こなす生活をしていれば、
この先もずっと消極的な息子のままだった思います。
『ぼくはこれをしたい!』という気持ちを表現できるようになりました!
②自分で考えて行動できるようになった
息子が通うのびのび幼稚園では、自分で何をして遊ぶかを考えたら、遊びの準備も自分でします。
- 園庭で遊ぶと決めたら、自分の帽子を取りに行く
- 工作をしたいと決めたら、お道具箱に道具を取りに行く
こんな感じで、自分が決めた遊びを実行するために、自分で考えて行動を起こすのです。
最近では、幼稚園で虫取りに夢中な息子が、『今日はバッタを捕まえるから虫カゴ持っていかなきゃね!』と、毎日虫カゴを自分で用意して登園しています。
そんな姿を見るたびに、子どもの自主性が育ってくれたと日々感じます。
『自分で考えて行動する』そんな力が身につきました!
③自分らしさを磨けるようになった
息子の通う幼稚園では、毎日子どもの自由が尊重されています。
苦手なことには参加しなくて良いので『できないこと』を注意される機会がありません。
入園当初にこんなことがありました。
汚れるのが苦手な息子は、泥遊びは一度もせずに毎日綺麗な格好で帰ってきます。
一方、泥んこが大好きなお友達は、いつも汚れた着替えを持ち帰っていました。
私はそんなお友達の姿を見て、
『あんなに毎日泥だらけですばらしい!息子も嫌がらずに泥遊びに挑戦すれば良いのに!』と思いました。
しかし担任の先生の反応は違いました。
『汚れたくなかったら無理してやらなくていいからね。』
と、息子に優しく言うのです。
私はその姿を見て、自分の考えを反省。
親の私が息子の苦手を尊重せずに、危うく『泥だらけの子どもの方が良い』と息子に決めつけてしまうところでした。
そんな息子は幼稚園に通う中で、工作が好きなことが分かりました。
息子は毎日のように、幼稚園で工作した空き箱を持ち帰ってきます。
ある日担任の先生に、『年少さんでダンボールをハサミで切れる子は初めて見ました!』と言われたことがあります。
泥だらけになるのは苦手。でもハサミを使うのは得意だと知りました。
自由保育では、自分の好きなことを磨く時間がたくさんあります。
そのおかげで、息子の得意なことを見つける機会が増え、苦手なことに消耗しなければならない時間は少ないように思います。
自由保育で日々、『自分の好き』を見つけて磨いてるような気がします!
お勉強はどこでカバーする?
一方、幼稚園に入園すると、お勉強は全くしていないことが分かりました。
なので同じ幼稚園のママ友に、
『幼稚園でお勉強しない分、他で補ったりしてるの?』と聞くと答えは3パターン。
我が家はいずれも試してみました。
①習い事として幼児教室に通わせてる派
幼稚園ではたっぷり遊び、幼児教室や習い事ではしっかりと勉強。
そんなメリハリをつけているご家庭もありました。
私も、『幼稚園の後には時間もあるし、せっかくだから習い事をさせよう』と、入園当初は息子を習い事に通わせていました。
しかし、息子は本当は幼稚園の後はゆっくりと過ごしたいことが分かり、結果的に辞めてしまいました。
②ドリルや絵本を使って自宅学習する派
幼稚園のお友達でドリルや絵本を使って読み書きができるようになったお子さんがいました。
私も『うちの子にもそろそろ読み書きを教えた方がいいのかしら?』と思うように。
私はさっそく、公文の読み書きドリルを買って自宅学習を試してみました。
すると、初めのうちは新鮮なので楽しんでいたのが、慣れてくると『やりたくない』と自主的にはやらなくなりました。
『ドリルやる?』『今はやりたくない』というやりとりが、親としても息子を勉強を強いてるような気持ちになり、結果的にドリルは辞めることにしました。
③うちは何もやってない派
ママ友のひとりに、『うちは勉強なんて何もやってないよ〜』といつも穏やかに過ごしているご家庭がありました。
子どものできないことに対して焦ることなくいつも穏やかなママ友の姿は私の中で斬新でした。
そんなママ友に影響を受け、『うちも焦らずに子どもが学びたくなるのを待ってみようかな』と決意。
すると、息子はドリルを辞めた後に、急にひらがなを覚えたい欲が高まり、結果的に自主的に辞書を引いてひらがなの読み書きをマスターしたのです。
人は必要に迫られた時に、自ら学習する力が備わってるんだなと思いました!
大切なのは園だけに子育てを任せないこと
子育てをする中で私が意識していること。
それは、『園だけに子育てを任せないこと』です。
日中の多くの時間を過ごす幼稚園が子どもに影響を大きく与えるのは間違いないと思います。
しかし、やはり教育の中心は家庭。
幼稚園はあくまでも家庭教育と並走する補助の教育だと思うと、
幼稚園への過剰な期待値も下がりました。
《お勉強幼稚園》と《のびのび幼稚園》。
どちらに通わせたとしても、基本はやはり『家庭教育が中心』と考え、幼稚園に足りない要素は家庭で補えば良いのではないしょうか。
小1プロブレムに対する私の考え
現在我が子が通うのびのび系幼稚園では、机に向かってお勉強する時間は全くありません。
このようなのびのび系幼稚園に通っていた園児は、『小学校に上がると座学についていけない』、『集団生活がキツい』と言う話を聞いたこともあります。
いわゆる『小1プロブレム』です。
しかしこれは、すべての責任が幼稚園にあると言えるでしょうか?
家庭の教育で、『人の話はしっかり聞く。』『食事の時は行儀良く座る。』といった基本のしつけを日々行うことも重要な役割のように思います。
子どもに合った幼稚園選びをしよう
自分の主張が苦手、集団では埋もれがちな息子はのびのび系幼稚園を選んで大正解でした。
一方、お勉強系幼稚園に通うお友達のお母さんで、『活発で言うことを聞かない息子は決められたルールの中で過ごすようになって、メリハリをつけれるようになった。』という話を聞いたこともあります。
どちらにも良い点があると思います。
そして、幼稚園では足りない部分は家庭で補えば良いのだと思います。
どちらが良い悪いではなく、あくまでも『自分の子どもにはどちらが合うか』の視点が大切ですね。
この記事が、幼稚園を選びで悩む方のお役に立てば幸いです。