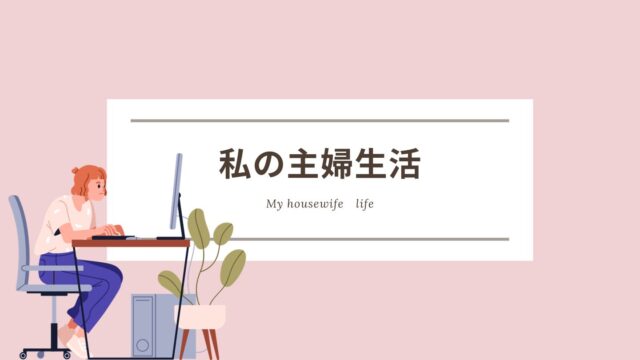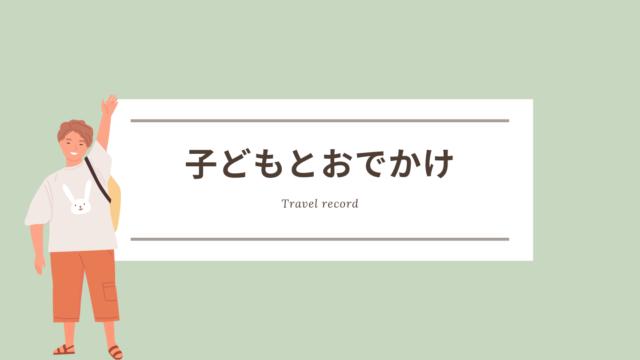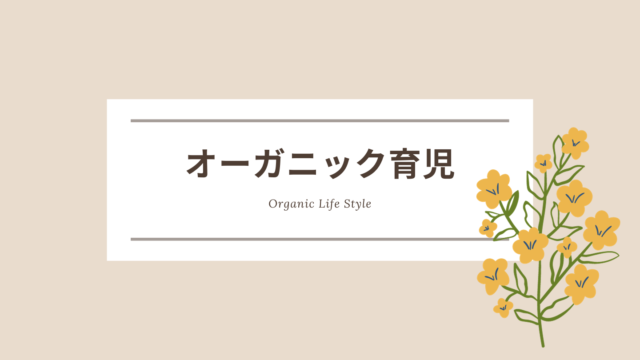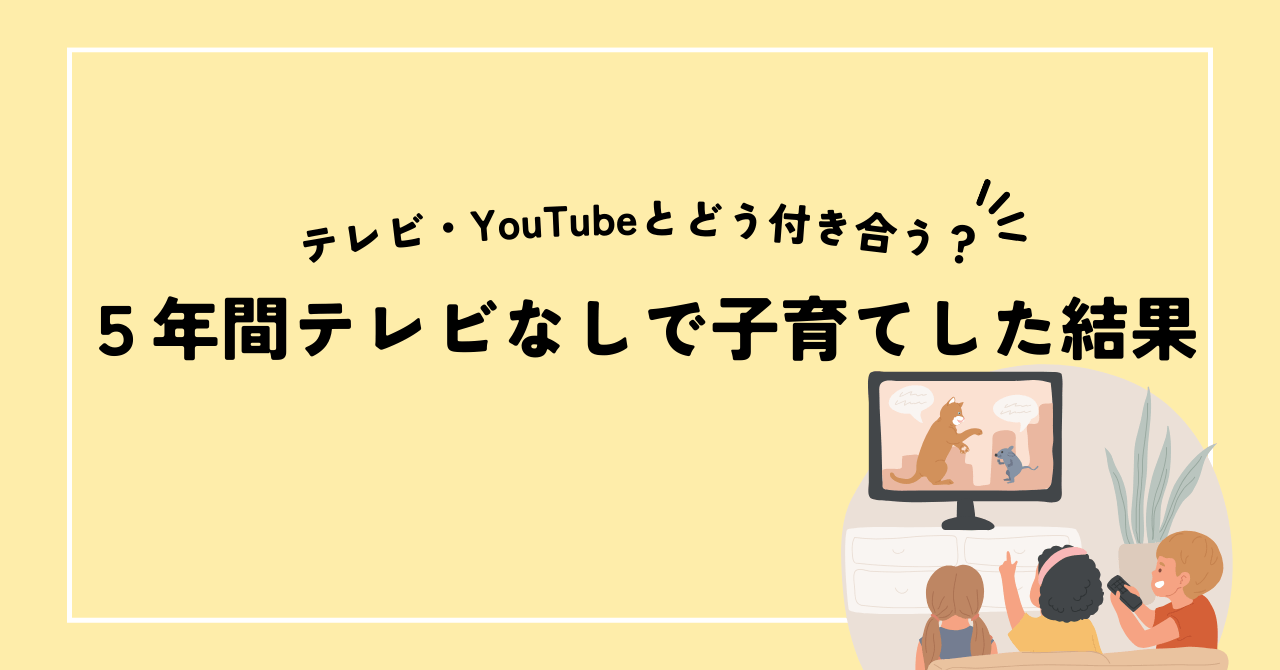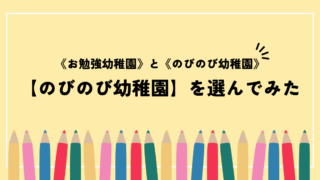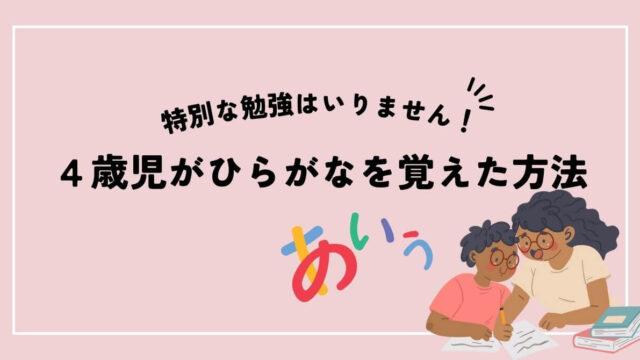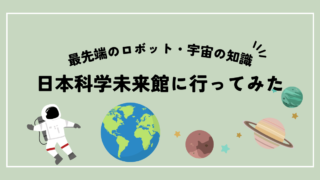こんにちは、まいたけです。
テレビなしで子育てをしています!
この記事では、テレビを持たない暮らしをする我が家の子育てを紹介します。
我が家がテレビを持たない理由
我が家がテレビを手放した理由は、夫がミニマリスト思考に目覚めたからでした。
テレビを手放したのは、息子が生まれてすぐのこと。
当初、私はテレビを手放すことには不安がありました。
情報を遮断すると、世間から切り離されるような気がしていたのです。
(ただでさえ、コロナ&育児で孤立してたしね…。)
しかし、いざテレビを手放しても何も困ることはありませんでした。
大きなニュースはネットでも流れてくる。
一方、余計なエンタメニュースは入ってこない。
テレビを手放したことで、メディアとちょうど良い距離感を掴めた気がしました。
子育て中心の忙しい日々で、
メディアに振り回されない生活はとても楽だと気づきました!
テレビを持たない子育てのメリット
夫婦で始めた『テレビを持たない暮らし』。
結果的に子育てにも良い成果をもたらしていると感じました。
①テレビの見過ぎで叱る必要がない
息子は赤ちゃんの頃からテレビを見る習慣がありません。
なので『テレビを見たい!』とグズグズすることもありません。
- 『子どもがテレビを見たいとぐずぐずする。』
- 『時間を決めても守れない。』
- 『外出先でYouTubeがないと静かにできない。』
我が家では、早いうちからテレビを見せずに子育てをした結果、
上記のような悩みをもつことはありませんでした。
育児の中で『テレビをやめなさい!』と叱らずにすむのはとても楽です。
②テレビの余計な情報が入らない
テレビを流していると、子どもには見せたくないような情報も流れてきます。
- 子どもには刺激の強い暴力事件などのニュース。
- 子どもの気持ちを煽るような、おもちゃやお菓子のCM。
- 幼い子どもの手本にならない大人の言葉遣い。
子どもはテレビに映るものを、なんでも『正しい』ように受け取ってしまいがちです。
テレビの刺激的な映像は、子どもの人格形成にも影響を与えかねないと思うのです。
③テレビなしで能動的に遊べるようになる
テレビを観る習慣がないので、息子の遊びはいつも能動的です。
朝起きたら、まず何を使ってどうやって遊ぼうかを自分で決めています。
『能動的な遊び』=自ら遊びを考え、自分で遊びを創造できる状態
『受動的な遊び』=映像やおもちゃに一方的に遊びを促されている状態
いつも能動的に遊んでいるので、
自分の時間の楽しみ方を自分で作ることができていると思います。
余談ですが、息子が能動的に遊ぶのが上手になった理由として幼稚園選びも大きかったと思います。
テレビなしで子育てした結果
息子は5歳になり、性格や個性もだんだんと現れてきました。
テレビなしで子育てしたことが影響しているなと思うことを書いてみます。
①性格が落ち着いている
息子は落ち着いた性格だと思います。
テレビを観る・観ないで親と揉めたり叱られることもないので、そういった影響もあると思っています。
息子は今戦隊モノのヒーローや、流行りのYouTuberにハマる年頃です。
しかし、そういった映像を見る機会も少ないので、良い意味で周りに影響されずに息子らしく育ってくれていると思います。
テレビを観ない代わりに、外では人との会話を楽しみ、家では自分の好きな遊びに取り組む。
こういった何でもない日常が、落ち着いた息子に育った理由だと感じています。
②言葉遣いが良い
性格が落ち着いていることに加えて、息子は言葉遣いも悪くないと思います。
相手を傷つけるような言葉を自ら発するタイプではありません。
しかし、息子も男の子。
お友達との関わりの中で悪い言葉ももちろん覚えて帰ってきます。
ふざけて楽しいくらいならそのまま見守るし、節度がなければ注意をしています。
今のところ、息子の言葉遣いの悪さに困ることはありません。
③自分の好きを知っている
いつも能動的に遊んでいる息子は、自分の好きな遊びがはっきりしています。
ロボットにハマっている今は、熱心にロボットのパンフレットを読み、ダンボールでロボットを作っていました。
息子は、継続的に好きなことに費やす時間がたくさんあるので、好きなことを伸ばすことができていると感じます。
幼少期にテレビで時間を潰してしまうのは、やはりなんだかもったいないですよね。
自分の好きなことを見つけてどっぷりハマる姿を見ると、親も嬉しくなります。
我が家流《メディアの楽しみ方》
我が家にはテレビを置いていませんが、プロジェクターとDVDプレイヤーを持っています。
プロジェクター=映画や音楽を流す
DVDプレイヤー=英語のDVD教材を流す
こんな使い分けをしています。
上記の媒体を使って地上波の映像をだらだらと流し見ることはありません。
主に、娯楽として映画や音楽を楽しんだり、教育として英語教材を流しています。
我が家が注意しているのは、いずれも『能動的に楽しむこと』です。
『能動的に楽しむ』とはどういうこと?
⇨テレビやメディアが選んだコンテンツを見せられるのではなく、
自分が楽しみたいと思ったコンテンツを自分で選ぶこと。
①朝や夜に音楽を楽しむ
朝起きたらプロジェクターから音楽を流します。
いつもYouTubeで検索しています。
(広告が流れるのは嫌なのですが、今は仕方ないと思って割り切っています。)
ゆったりとしたJAZZをBGMにしたり、クラシックや80年代の洋楽を流したり。
子ども向けの曲は流しません。
音楽には年齢の垣根はないと思うからです。
幼い頃に聞いた音楽は教養として身につき、
一生楽しめるものになると考えています。
②休日には家族で映画を楽しむ
お休みの日には家族3人で映画を見ています。
ポップコーンを用意して、みんなが楽しめる映画を観ます。
トイストーリー、レミーのおいしいレストラン、リメンバーミー。
内容はやっぱり今はディズニーに寄りがちかな。
トトロ、千と千尋の神隠し、魔女の宅急便も楽しみました。
ジブリ映画は昔の日本や、海外の異文化など学びも多いです。
この習慣は息子が大きくなっても続いて、
家族で共通の楽しみになれば良いなと思います。
③息子の興味に合わせてYouTubeを観る
息子はロボットが好きなので、YouTubeでロボットの動画を見ることもあります。
しかし、YouTubeは一度見始めると延々と見たくなってしまいます。
なので時計を見ながら時間を決めて見るようにしています。
YouTubeを観るのに特にルールは設けていません。
- 『今日は休日だから30分だけ見てみようか』
- 『朝も見たから今日はお休みしようね。』
- 『毎日見ると頭が疲れちゃうから今度のお休みに見ることにしよう。』
と、毎回親のさじ加減で視聴を許可するのです。
どうしてルールを決めないかというと、『1日何分まで』と決めるとどうしても時間をフルに使って観ようとしてしまいます。
我が家では、ルールは決めずに、いつでも親が主導権を握りながら視聴を許可するようにしています。
④英語のDVD教材を観る
我が家は教育として英語のDVD教材を購入しています。
気が向いた時に、週に3、4回は流しています。
流し始めると息子はぼーっと観ることもあれば、遊びに夢中で観ていない時もあります。
両親が英語を教えることができればDVDを流す必要もありません。
しかし、英語ができる両親ではなかったのでこれは仕方がないかなと割り切っています。
ただ、同じDVDを5年間繰り返し見ているので、『見たい!』とぐずったり、時間が守れないというトラブルはありません。
英語も少しずつ身につき、耳も慣れているようで、英語のDVD教材は取り組んで良かったなと思っています。
【まとめ】メディアとの良い付き合いをしよう
メディアは依存性があるので、子どもとの付き合いかたは注意しなければなりません。
一方で、メディアは親が見せることができない世界を広げてくれるツールでもあります。
テレビやメディアは良い点、悪い点、どちらもあり。
上手に付き合っていくことが必要でしょう。
それぞれの家庭にあった付き合い方がきっとあるはずです。
この記事が、子育て中のテレビとの付き合いを検討している方の参考になれば幸いです。